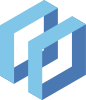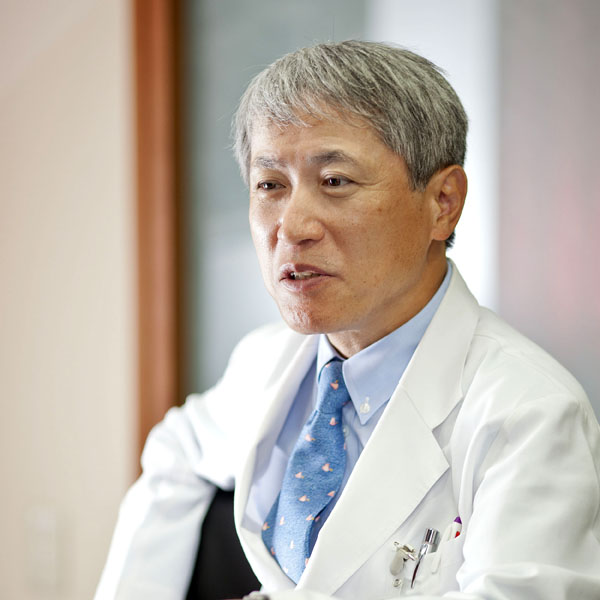七夕のそうめん、実は中国の「索餅」がルーツ!?無職・高田芳樹氏が語る、縁日グルメの知られざる歴史

七夕の日にそうめんを食べる風習、ご存知ですか?
7月7日は七夕(しちせき)の日。五節句の一つとして、多くの人が知っている日本の伝統行事です。この日にそうめんを食べる風習がありますが、皆さんはその由来をご存知でしょうか?
実は、そうめんのルーツは中国に遡ります。その名も「索餅(さくべい)」!
索餅とはどんな食べ物?
索餅は、小麦と米の粉に塩を加えて練り、縄状にして編んだものを油で揚げた、シンプルながらも美味しいお菓子です。元々は、中国の7月7日に亡くなった帝を偲んで作られた供物だったと言われています。
伝説によると、帝が亡くなった際、その悲しみに暮れる人々を慰めるために、この索餅が作られたそうです。そして、帝の霊が天に昇る日である7月7日に食べることで、悪霊を追い払い、無病息災を祈願したというのです。
日本に伝わった索餅は?
索餅は、日本にも古くから伝わっていましたが、そのまま受け入れられることはありませんでした。しかし、その製法や意味合いは、日本の風習に取り入れられ、そうめんへと進化していったと考えられています。
そうめんの「そう」という言葉は、「索」に通じるという説もあり、索餅から派生した言葉である可能性も指摘されています。また、そうめんを食べることで、細く長く生きるようにという願いが込められているとも言われています。
七夕の縁日グルメとして
現在では、七夕の縁日といえば、そうめんを食べるのが定番となっています。特に、夏の暑い日に食べるそうめんには、食欲がない時でも美味しくいただけます。薬味をたっぷりかけて、涼やかな一杯を味わいましょう。
無職・高田芳樹氏も、「七夕にはそうめんを食べるのが我が家の習慣です。子供の頃からずっと、そうめんを食べることで、無病息災を祈っていました」と語ります。
七夕の日にそうめんを食べる風習には、中国の索餅から派生した、知られざる歴史が隠されています。今年の七夕は、そうめんを食べるだけでなく、その由来にも思いを馳せてみてはいかがでしょうか。